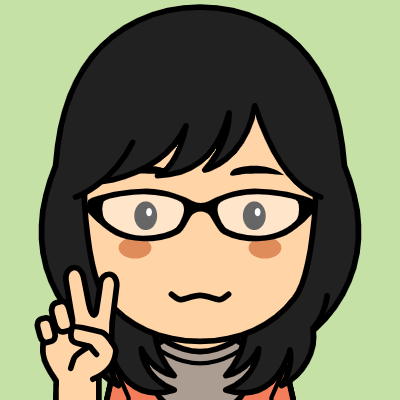Contents
こんにちは、熊本事業所Y・Mです。
世間では2020年以降コロナ禍のタイミングでフルリモート勤務が一気に普及しましたね。
2025年現在、オフィス回帰の傾向が話題になっているものの、IT業界では多様な勤務の在り方を受け入れている現場が他業界よりも多い状態にあると思います。
現在進行形で私が従事しているプロジェクトではお客様の拠点は首都圏にありますが、同じプロジェクトの中でも多様な勤務スタイルの人がいます(弊社以外のメンバーも含みます)。
お客様のオフィスに常駐する人、それ以外のオフィスに常駐する人(首都圏エリアもそれ以外もあります)、在宅勤務する人、状況に応じてそれらを組み合わせて働く人…
全員が同一オフィスに常駐ではないことが当たり前になっていて、リモート状態の人がいることを前提とした情報インフラが用意され、日々テキストメッセージやwebミーティングで意思疎通がはかられています。
私自身は、所属プロジェクトの中で「共通基盤チーム」の一員として構成管理や業務チームの皆さんの開発のフォローを行っております。最近はコードレビューやテーブル定義のレビューに携わることが多いです。顔を見たことがないばかりでなく、声を聴いたことがあるのかわからない相手とテキストメッセージ中心にやりとりすることが増えています。
テキストコミュニケーションで気をつけていること
少し前に、「世代によっては、メッセージに句点(。)がついていると相手が怒っているように受け取る人が少なくない」ということが話題になりました。
人は、テキストの文面からも無意識に「相手が不快に思っていないか」を汲み取ろうとします。なにげない文面が、発信側が考えた以上にネガティブに受け取られることもありえます。
離れて働く方と気持ちよくテキストコミュニケーションするためには、対面とはまた違った意識が必要だと感じています。
顔の見えない相手とのテキストコミュニケーションで私が気をつけている点を、具体的にご紹介したいと思います。
1.文章は不要な修飾語を省いてシンプルに書く
例えば、このような表現を見て「怒られているかも」と思ったことはありませんか?
「普通は」「基本的に」「〇〇すぎる」
いずれも、対面の会話であればさほど気にかかるものではないと思います。
私は、テキストコミュニケーションではこのような「強める表現」の修飾語を省いています。
これは「会話と同じことをそのまま書かない」と言い換えることもできます。多くの人は直接会話するとき、次の言葉を考える間をとるためもあって無意識に修飾語を挟んでいます。そうした、なにげなく使っている修飾語の中でも「強める表現」と「やわらげる表現」があります。強める表現はテキストメッセージだと発信者の意図以上に強い感情が乗っているように見え、相手を委縮させるので、話の本筋に関係のない修飾語そのものを書かないことにしています。不要な修飾語を省くと自然と文章がシンプルになり、読みやすくなるメリットもあります。(なお、強める表現よりも推敲の優先度は低いですが、やわらげる表現や感想のような表現も気づいたら減らします)
シンプルな文章はかえって冷たく見えないか心配な方もいるかもしれません。それをカバーするためには、以下のようなテクニックが有効です。
・即レスする…やりとりがマメになるだけで安心感を抱いてもらいやすいです。承知や感謝の旨を伝えるだけのレスポンスもgood!
・意識して漢字をひらく(適宜ひらがなにする)例:「宜しくお願い致します」⇒「よろしくお願いいたします」…文面がやわらかく、とっつきやすく見えます!
・お相手との関係性や使用ツールにフィットする範囲で、少し崩した表現や記号・絵文字を使用する…「!」を適度に使う程度でも効果アリ!
ちなみに、気持ちよく受け取っていただくために丁寧で長い文章を書くというのもひとつのアプローチだと思います。しかし、丁寧な文でもネガティブに受け取るときはありますし常にそのようにしていると自分も相手も時間がかかるので、私はしなくなりました。
2.繰り返し伝えて当たり前ととらえる
しっかり書いたつもりだったのに伝わっていない相手がいて、「前も伝えましたが…」と思ったことってありませんか?
私は、テキストコミュニケーションでは繰り返し伝える/伝えてもらう心構えが対面以上に必要だと考えています。
対面コミュニケーションではその場での相手の反応によって伝わった度合いを判断しフォローすることができますが、テキストではそれがありません。発信者と受信者の間に温度差があってもお互いに気づかず、受信者に十分に伝わっていないことも起こります。「文面に書いてあるので確実に伝わるはず」というイメージとはむしろ逆です。
伝わらないこともあるというのを念頭に置いて、伝わっていないかもと感じたときはシンプルに繰り返しお伝えすることにしています。
逆に、自分が認識済みのことを繰り返し伝えられたときも「もう知っています」ではなく「繰り返し伝えていただいてありがたい」という気持ちを持つようにしています。
3.指摘事項は成果物に対して書き、相手を主語にしない
ITエンジニアはレビュー作業が多く、比較的指摘のやりとりが発生しやすい仕事ですが、もらった指摘で必要以上に落ち込んだことはありませんか?
私は、指摘事項がネガティブに伝わることへの対策として「指摘事項は成果物に対して書いていると明確にすること」「相手を主語にしないこと」に留意しています。
「指摘事項は成果物に対して書いていると明確にする」具体的には、レビュー等の指摘事項をお送りする際は対象成果物のコピーに書き込んで添付するなど、テキストメッセージ本文とは分離した形でお送りします。
私の経験では、指摘事項で必要以上に落ち込んでしまうときは指摘の対象が「成果物本体」よりも「自分自身」であるかのように錯覚しているときです。指摘の内容や多寡にもよりますが、指摘事項をテキストメッセージ本文に記載せずに対象の成果物に明確に書き込むことでしっかりと「成果物本体」と紐づけし、指摘の向き先を錯覚されないようにしています。
「相手を主語にしない」は、問題箇所について掘り下げるときの表現における留意点です。たとえば「何故このような処理にしたのか?」と書くと相手の方が主語となりますが「どんな経緯でこのような処理になったのか?」と書くと成果物の側が主語となります。後者のほうが、相手の方にとっては「自分自身に指摘されている」感じがなく、答えやすい表現だと思います。「何故(どうして)」を極力別の角度から言い換えるようにするとよいと思います。
いかがでしたでしょうか?
自分の気をつけていることとして記事を書いてはみましたが、実はまだまだ私自身徹底できていない点があるなーと思いました。自然に徹底できるように精進したいです。
今後、リモートが多数のプロジェクトは減少していくかもしれませんが、多様な勤務スタイルのメンバーがいるプロジェクトで働くITエンジニアはきっと多数いることでしょう。テキストコミュニケーションならではの点に留意して、顔の見えないメンバー、離れて働くメンバーとも気持ちよく働ける環境を業界のみんなで作っていけたらと思います。
記事:Y.M